海外で注目を集める10個のサービス・アプリについて、日本市場での展開状況をまとめます。それぞれ公式に日本展開されているか、日本でのユーザー数や利用動向、日本のメディアでの話題性、そして未展開の場合の参入予定や障壁を解説します。
BeReal(ビーリアル)
フランス発のSNS「BeReal」は、日本でも公式に利用可能です。アプリは日本語にも対応しており(実際、サポートサイトは日本語表示されています)、2023年頃から日本の若者を中心に急速に普及しました。日本はBeRealにとってアメリカに次ぐ第2の市場で、2025年3月時点の月間アクティブユーザー数(MAU)は約450万人に達しています 。ユーザーの83%が14~27歳のZ世代で、特に高校生の約3割が毎日BeRealを利用している計算になります 。これはありのままの瞬間を友人と共有するというコンセプトが、日本のZ世代にも受け入れられた結果といえます。「盛らないSNS」としてテレビやウェブメディアでも紹介され、日本独自の広告展開も始まりました。2024年にBeRealが仏ゲーム会社Voodooに買収された後、日本市場は主要ターゲットと位置づけられ、ユニクロや資生堂など日本企業もBeReal上で広告キャンペーンを展開しています 。今後もZ世代以外の層への利用拡大が目指されており、日本語ローカライズやコミュニティ施策も強化される見込みです。
Lensa AI(レンザAI)
写真をAIでアバター化できる編集アプリ「Lensa AI」は、世界的なブームとともに日本でも利用可能です(※UIは英語ですが直感的に操作できます)。2022年末に追加された「Magic Avatar」機能がSNSで拡散され、App Storeの有料ランキングでトップを独走するほど爆発的人気となりました 。日本でもTwitterやInstagram上で、自分の写真が生成した幻想的なアバター画像を共有する投稿が多数見られ、一時大きな話題となりました。ただし**日本語の公式展開(ローカライズ)**はまだで、アプリ内表示は基本英語です。それでも操作はシンプルなため、日本人ユーザーからの評判も上々です。国内メディアでも「海外で話題のAIアバター化アプリ」として紹介され 、利用時の注意点(写真データの取り扱いやAIによる過度な美化・バイアスの問題)も報じられました 。実際、一部の女性ユーザーから「肌の露出が勝手に増やされた」「不自然にスタイルが盛られた」といった指摘もあり 、Lensa開発元はプライバシー保護や生成バイアスの改善に取り組むと発表しています。ブーム後はピーク時ほどの騒がれ方は落ち着いたものの、写真加工アプリとして引き続き利用するユーザーもおり、日本のApp Store/Google Playからダウンロード可能です。今後、日本語対応や国内向けプロモーションが行われれば、再び注目を集める可能性があります。
Notion(ノーション)
オールインワンのドキュメント・データベースツール「Notion」は、2021年に日本語ベータ版を公開して以来、日本市場に本格展開しています。2022年6月には東京に日本法人「Notion Labs Japan合同会社」を設立し、同年11月に日本語版を正式リリースしました 。公式サイトやアプリは日本語表示に対応し、サポート体制も強化されています。こうしたローカライズの成果もあり、日本での利用者は急増しました。ベータ版リリース前後でチーム向け利用の新規開設数が前年比2.7倍になるなど企業での導入が加速し 、スタートアップから大企業まで幅広い層が活用しています。実際にトヨタ自動車や三菱重工といった日本の大企業も社内情報共有にNotionを採用しており 、「エバーノートに代わる次世代ツール」としてビジネス誌やIT系メディアで多数取り上げられています。個人ユーザーでも、日本語対応前から熱心なファンが存在し、SNS上でテンプレートや活用法が共有されてきました。日本語版の正式提供後はさらなる一般層への普及が進み、ノートやタスク管理ツールとして学生やフリーランスにも広がっています。今後もコミュニティイベントやユーザー事例の発信を通じ、日本市場での存在感を一層高めていくでしょう。
Duolingo(デュオリンゴ)
世界最大級の語学学習アプリ「Duolingo」は、早くから日本市場に参入しています。日本語話者向けには英語やフランス語など多数の言語コースを提供しており、アプリ・サイトとも日本語対応済みです。2020年末に日本公式Twitterアカウントが開設され、本格的なマーケティング展開が始まりました。以降、日本の利用者数も順調に増加しています。2023年には日本国内の教育カテゴリーでダウンロード数・収益ともにトップとなり、ビジネスが急成長しました 。グローバルでは月間アクティブユーザー数1億人を超え、語学アプリ市場の約9割のシェアを占めると言われ 、日本でもその勢いが反映されています。特に若年層の英語学習や、逆に海外のユーザーによる日本語学習で利用されており、「学習熱心な国」ランキングで日本は世界有数とのデータもあります (Duolingoの年次報告で2022年に日本が熱心度1位、2023年は2位と発表)。こうした実績から、Duolingo社は日本にカントリーマネージャーを置き(現在は水谷翔氏)、学校教育への提案や企業連携も模索しています。NHKなどでも「スキマ時間で学べるアプリ」として紹介され、マスコットのフクロウ「デュオ」も徐々に認知度を上げています。日本市場では英語学習アプリは競争が激しいものの、基本無料でゲーム感覚というDuolingoの特徴が支持を集め、今後もユーザー層の拡大が見込まれます。
Canva(キャンバ)
デザイン作成プラットフォーム「Canva」は、オーストラリア発ながら日本展開に非常に積極的です。2020年頃より日本ユーザー向けのローカライゼーション戦略を本格化し、日本専用のテンプレート開発や日本語フォントの追加などを行ってきました 。2021年には東京にCanva Japan株式会社を設立し、日本人スタッフによる運営・サポートも開始されています 。現在、ウェブサイト・アプリとも完全に日本語対応しており、操作メニューからチュートリアルまで日本語で利用可能です。さらに、日本独自機能として年賀状や名刺、履歴書などのテンプレートを数千点用意し、ブログサービス「note」や「はてなブログ」と提携してCanvaボタンを導入するなど、日本のユーザー習慣に合わせた施策も展開しています 。2024年には人気イラスト素材サイト「いらすとや」と正式提携し、2万点以上のイラスト素材をCanva上で利用可能にするなど話題を呼びました 。こうしたローカル対応の強化により、日本国内の個人・企業ユーザーは増加しており、SNS用画像や資料作成ツールの定番の一つとなりつつあります。Canva自体は全世界で1億8,500万人以上が利用するサービスで 、日本でもスタートアップ企業のデザイン業務や教育現場での活用事例が紹介されています。競合のAdobe製品に比べ手軽さが評価され、「Photoshopがなくても色々作れるCanva」として一般メディアでも取り上げられています。今後も日本市場向けに機能改善が続けられる予定で、2024年にはUIのひらがな表示モード(小学校低学年向け)も追加されました 。日本のユーザーからのフィードバックを積極的に製品に反映しており、長期的に日本で根付いたサービスになることを目指しています。
ChatGPT(チャットGPT)
OpenAI社の対話型AI「ChatGPT」は、日本でも広く利用可能で大きな社会現象を起こしました。2022年末のサービス公開直後から日本のSNSやニュースで注目され、2023年には「ChatGPT」という単語自体が流行語候補になるほど話題となりました 。実際、ソフトバンクの孫正義社長が「まだChatGPTを使っていない人は人生を反省した方がいい」と発言してニュースになる など、日本でも多方面で取り上げられています。公式の日本語対応UIは未提供ですが、日本語の質問にもしっかり答えられる性能だったため、言語の壁なく利用が広がりました。2023年5月には公式のiOS版アプリが日本でもリリースされ、スマホから手軽にチャットできる環境も整いました(Android版も追随)。こうしたユーザーの盛り上がりを受け、OpenAIはアジア初の海外拠点として東京オフィスを開設し、2024年4月には日本法人「OpenAI Japan」の設立を発表しています 。同時に日本語に最適化されたGPT-4モデルの提供も開始し、日本企業向けのカスタムAIソリューション展開に乗り出しました 。既にダイキン、楽天、トヨタコネクティッドなどがChatGPT Enterpriseを導入し業務効率化に活用しているほか 、神奈川県横須賀市など自治体でも住民サービス向上のため試験利用が行われています 。一方で、学校教育現場では生徒の不正利用を懸念する声や、企業でも機密情報入力への注意喚起がなされるなど、利活用ルール作りも課題となっています。総じてChatGPTは日本市場で非常に大きなインパクトを与えており、政府もG7広島AIプロセスの主導など政策面で関与しています。今後は日本語版UIの整備やさらなるモデル改良も期待され、ビジネスから個人まで幅広い層への定着が見込まれます。
Locket Widget(ロケットウィジェット)
ホーム画面上で写真をシェアできるユニークなアプリ「Locket Widget」は、海外でのブームが日本にも紹介されています。アプリ自体は日本のApp Store/Google Playからダウンロード可能ですが、UIは現状英語表示のみです。それでも操作はシンプルなため、日本でも一部の若者が利用しています。Locket Widgetは最大20人の限られた友人や家族とだけ写真を共有できるのが特徴で、投稿写真に加工や公開範囲の煩わしさがない「ミニSNS」としてZ世代に注目されました 。TikTokで機能が拡散され、2022年には米国App Store総合1位を記録する大ヒットとなったことから、日本のメディアでも「次に流行るかも?」と取り上げられています 。実際、Appleの2022年App Store Awardsでは「今年のカルチャーインパクト」部門としてLocket Widgetが紹介され、「大切な人を身近に感じられる素晴らしくシンプルなApp」と評価されました 。日本でも2023年頃からSNS上で「友達同士でLocketを始めてみた」といった投稿が散見され、一部のインフルエンサーがPRを行う動きもあります 。ただし現時点では利用者は限定的で、Instagramなど既存SNSの強力な代替とまでは至っていません。日本語未対応ゆえのハードルも指摘されていますが、「UIを日本語化してほしい」というユーザーの声もあり、開発者が今後ローカライズに関心を示せば日本でブレイクする可能性を秘めています。いずれにせよ、「親しい人とのクローズドな写真共有」という新しいコミュニケーション手段として、日本でも静かな広がりを見せているサービスです 。
Too Good To Go(トゥー・グッド・トゥー・ゴー)
食品ロス削減のためのアプリ「Too Good To Go」は、欧米や一部の地域で大成功していますが、日本ではまだ公式展開されていません。アプリ自体は日本のストアから入手できない状態で、利用しようとしても対応エリアに日本が含まれないため使えません 。しかし、日本にもこれと似たコンセプトのサービスは存在します。例えば**「TABETE(タベテ)」というアプリは、飲食店の余剰食品を消費者がお得に購入できるプラットフォームで、環境省のグッドライフアワードを受賞するなど注目されています 。TABETEでは、お店が「まだ美味しく食べられるのに廃棄せざるを得ない食品」を独自メニューとして出品し、ユーザーが事前決済して受け取りに行く仕組みで、まさにToo Good To Goの日本版と言えるサービスです 。このほか「Reduce GO」や自治体主導のフードシェア施策など、日本市場には独自のプレーヤーがいるため、Too Good To Go本体は参入を見送っているのかもしれません。日本ではスーパーやコンビニで閉店前に値引き販売する文化(いわゆる「見切り品」)が根付いていることもあり、アプリを介さずとも食品ロス削減が一定行われています。もっとも、国内の食品廃棄量は年間643万トンにも上り 、課題は依然大きいです。Too Good To Go社もこの市場性には関心があるようで、公式サイトには日本語で企業ミッションや実績(19か国で1億人以上のユーザー、累計3.5億食の食品ロス削減など)が紹介されています 。2025年開催の食品展示会(FOODEX)向けに日本語ページを用意する動きも見られ、将来的に日本参入の可能性**がないわけではありません。現状では「未上陸」と言えますが、日本の消費者や事業者のフードロス意識が高まれば、公式展開が検討されるかもしれません。
Flo(フロー)
世界的に人気の月経管理アプリ「Flo」は、日本語にもしっかり対応してサービスを提供しています。イギリス発のFloは、生理周期や排卵日を予測するためにAIで70以上の身体症状をトラッキングできる高度なアプリで、日本語を含む20言語以上にローカライズ済みです 。そのためアプリ内の表示やヘルスレポート、Q&Aコラムまで日本語で読むことができ、日本のユーザーにも利用しやすくなっています。実際、日本国内のApp Storeでも「生理周期管理・排卵トラッカーFlo」として配信されており 、レビューには「シンプルで使いやすい」「パートナーと情報を共有できて便利」といった声が見られます 。もっとも日本には、月経管理アプリとして老舗の「ルナルナ」など独自の人気アプリが存在するため、Floのシェアがどれほどかは公表されていません。それでもグローバルでのユーザー数は3億8,000万人以上、2024年6月時点の月間アクティブユーザー数約7,000万人という規模を誇り 、国内でも相当数のユーザーがいると推測されます。日本のメディアでもフェムテック関連の文脈でFloはたびたび紹介されており、2023年には巨額の資金調達でユニコーン企業になったニュースが報じられました 。さらに、Floはプライバシー保護にも力を入れており、米国での匿名モード機能導入などが話題になった際には日本語ブログで公式説明がなされるなど、ユーザーの信頼確保に努めています。今後は更年期ケアなど新領域へのサービス拡大も計画されており 、引き続き日本の女性の健康管理ツールの一つとして存在感を示していくでしょう。
Runway(ランウェイ)
生成AIを活用したクリエイティブツール群を提供する「Runway」は、日本にオフィスこそありませんが、クリエイターやAI開発者の間で注目されています。Runwayは映像や画像の編集・生成を行える統合プラットフォームで、特にテキストや画像から動画を作り出す最新AIモデル「Runway Gen-2」で知られます 。このGen-2モデルは、入力した文章の指示に沿って短い動画クリップを自動生成できる画期的な技術で、海外では映画制作の現場にも採用され始めた注目のAIです 。日本のユーザーもRunwayのサイトに登録すればサービスを利用可能で、既に映像制作系のコミュニティでは「試してみた」「こんな動画ができた」という報告がSNSやブログで共有されています。操作画面は残念ながら日本語非対応ですが、UIはシンプルでドラッグ&ドロップ中心のため直感的に利用可能との声もあります 。国内のAI解説サイトやYouTubeでは、Runway Gen-2の使い方や機能紹介が多数公開されており、商用利用の可否や料金プランについて日本語で解説する記事も増えてきました 。たとえば無料プランでは動画生成にいくつか制限がありますが、プロプランに契約すれば無制限に高解像度動画を書き出せること、また生成物の商用利用も可能であることなどが紹介されています。日本の一般メディアではまだ馴染みが薄いものの、クリエイティブ業界では「生成AI動画の最先端」としてRunwayの名前が知られてきています。今後、日本語対応が進んだり国内企業と連携したりすれば、一気に利用が広がる可能性があります。現時点では英語版をそのまま日本から使う形ですが、技術に敏感なクリエイター層を中心に日本市場でも密かな注目を集めているサービスです。
まとめ
以上、海外発の10サービスの日本市場での状況を見てきました。既に日本に深く根付いているもの(NotionやDuolingoなど)もあれば、これから本格展開が期待されるもの(Too Good To Goなど)もあります。それぞれのサービスが日本のユーザーや文化に合わせた展開をすることで、さらに多くの人に受け入れられていくでしょう。本記事が、新しいサービスとの出会いや理解の一助になれば幸いです。

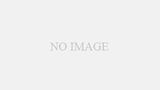
コメント
ya53sf